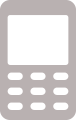目頭切開術は、目頭の皮膚を切開して目の横幅を鼻の方へ広げ、目を切れ長の大きく見せる手術です。


目頭切開法は、目頭部分を覆っている蒙古襞(もうこひだ)を切開し、目頭部分のピンクの肉(涙丘)を見せる手術です。 これによって、目の横幅が長くなり目が大きく見えます。
目と目の距離が狭くなるため、鼻筋が通ったような印象を与えます。また、平行型の二重を作る際に必要となる場合もあります。
目頭切開法には様々な術式がありますが、目の状態に合わせて適した術式で行います。

蒙古襞を切開
![]()

目頭切開後

Z形成は、皮膚を切除せずに目頭をZ型に切開し、縫合時に皮膚弁を入れ替えて縫う術式です。
皮膚弁を入れ替えて縫合することにより、蒙古襞の緊張が緩み、皮膚のひだを鼻側に移動することによって、ひだの裏に隠れている本来の目頭が見えるようにします。
Z形成は、弁の作り方が調整可能で、目の状態やご希望に合わせて、最適な方法を選択します。
皮膚を切除するW法に比べて、傷跡・赤み・ダウンタイムを抑えられ、手術後に目頭を元の状態にある程度修正することが可能です。

蒙古襞を上下2か所の三角形で切開+切除する術式です。余分な皮膚を切り取るため、後戻りが少なくしっかりイメージの変化を出せます。
横だけではなく、縦方向にも目の開き幅を大きくすることができ、Z法よりも平行型の二重に近づけることができます。
また、目頭側のみのたるみ取りも行えるのが特徴です。
Z法に比べダウンタイムが多少長いのと、皮膚を切除するため、元の状態に戻すのは困難です。

リドレープ法は韓国で多く用いられている目頭切開の術式の1つです。
「韓流目頭切開」とも呼ばれており、二重ラインを顔の内側に広げるように切開し、張っている蒙古ひだを取り除いていきます。
切開はほぼ皮膚の内側になるため傷跡が見えにくいですが、控え目な変化になることが多いため、あまり変化を感じれないケースがあります。
| 施術時間 | 20~30分程度 |
|---|---|
| 施術後の通院 | 7〜14日間に抜糸のためご来院いただきます。 |
| 痛み止め/化膿止め | 化膿止め、痛み止めをお出ししております。 服用によって何らかの異常がおきましたらば服用を中止して当院までご連絡ください。 |
| 抜糸 | 必要です。 |
| 麻酔 | 局所麻酔 |
| ダウンタイム | ダウンタイム・術後経過には個人差があります。 手術後は腫れやむくみがあり、ご希望と異なると感じることがありますが、しばらくお待ち頂くことでご希望通りに落ち着きますので安心ください。 |
|---|---|
| 術後の腫れ | 約7日間(目頭部分から目の周りに出る可能性もあります) 内出血や感染症になった場合、腫れが長引く事もあります。 |
| 内出血 | 注射針が当たるか、手術操作によって細かい血管が傷つくと、皮膚の下で出血します。 その際に、紫色になりますが、1~2週間で消失します。目頭から目の周りに出る可能性があります。 また、白目に内出血が出現すると白目の一部が赤く見えますが、こちらも1~2週間で消失します。 |
| 抜糸 | 7~14日目(目頭についている糸を2回に分けて抜糸します) |
| コンタクト | 当日から可能ですが、ゴロゴロと違和感があるときは中止して下さい。 |
| メイク | アイメイクは抜糸の翌日から可能です。 その他の部分は手術当日から可能です。 |
| 術後の通院 | 7日目、14日目 |
| 完成 | 約3ヶ月 |
| まぶた | 腫れやムクミにより、左右差が生じる、目頭が見えすぎることがあります。傷口を縫合することでドッグイヤーと呼ばれる皮膚の余りが生まれることがありますが、術後1~3ヶ月で徐々に改善されます。 |
| 加齢による変化 | 手術後もタルミにより目頭部分の形が変わるなど、加齢による変化は引き続き起こります。 |
| 傷 | 傷の赤みは数ヶ月かけて薄茶色(色素沈着)から白っぽい線へと変化し改善します。 |
※喫煙は血液の循環を悪くする為、傷の治りが悪くなります。また、細菌がついて感染を引き起こす原因にもなります。術前2 週間前~術後最低1ヶ月は禁煙をお願い致します。
※手術後3ヶ月間は、腫れや炎症が残っているため、手術を行うと、傷が汚くなる、癒着(ゆちゃく)が強く変形するなど、原則として調整や手術は行えない時期です。腫れや炎症が収まる3ヶ月以降に判断し、調整を行わせて頂くことを御了承下さい。
※文中の『術後』の表記においては、初回手術を基準とさせて頂きます。
A) 目頭の開きが足りない
B) 目頭が見え過ぎてると感じる
C) 目頭の形の左右差
D) 平行型の二重にならない
E) 傷跡が気になる
F) 涙管(涙の流れる管)の損傷
G) 感染(化膿する)
H) 血が溜まる
I) 傷が開く
J) 白目や角膜の損傷
K) 眼球の火傷
| トラブルの内容 | 対応 | |
|---|---|---|
| A) 目頭の開きが足りない | 目頭のピンクの肉が完全に露出しますと、不自然な目元になる可能性が高いので、目頭切開はやや控えめにして蒙古襞を一部残すようにします。その結果が物足りなく感じるかもしれません。 また、術後にキズが縮むことによって後戻りが生じることがあります。 目頭を完全に露出させるように切開しても、目の横幅の延長や、目と目の近づく効果が物足りないことがあります。 |
目頭のピンクの肉の露出が少ないためもっと目頭を広げたいと希望される場合、目頭切開を再度行います。 ※目の横幅の延長効果には、限界があることをご理解ください。 |
| B) 目頭が見え過ぎると感じる | 目頭に糸がついている間は、糸で傷口が引っ張られて目頭が見え過ぎていると感じることがあります。 目頭切開によって、目と目が1mm近くなるだけで顔の雰囲気はかなり変わります。そのため、目頭切開の術後に目元がシャープになり過ぎたと感じたり、目頭のピンクの肉が見え過ぎると感じるこがあります。 |
目頭の糸がついている間は、目頭が見え過ぎてしまうことがありますので、まずは抜糸が済むまでお待ちください。 目頭切開による顔の雰囲気の変化に最初はとまどうことがあるかもしれませんが、数ヶ月経過すると見慣れてきます。 傷が落ち着いた後も目頭の露出が気になる場合には、目頭に皮膚を被せるモウコヒダ形成術を承ります。 ※ただし、蒙古襞形成術を行いましても、完全には手術前の状態に戻せないことをご了承ください。 |
| C) 目頭の形の左右差 | 目頭の切開線の長さや位置のわずかなズレ、術後の傷の縮みの左右差がありますと、目頭に露出するピンクの肉の形や大きさに左右差が生じます。 | 左右差が生じた場合、基本的に、開きが足りない側(片側)の目頭を再度切開して調整致します。 |
| D) 平行型の二重にならない | 元々の二重の幅が狭いと、目頭切開を行なったとしても平行型にならないことがあります。 | 手術後、平行型の二重にならない場合は、さらに目頭を広げるか、二重の幅を広げる手術が必要となります。 |
| E) 傷跡が気になる | 質により、傷跡がケロイドのように赤く盛り上がることがあります。ほとんどの場合、術後3ヶ月程で治まってきます。また、逆に傷跡が凹んでしまう可能性もあります。 | 体質により、傷跡がケロイドのように赤く盛り上がることがあります。 また、逆に傷跡が凹んでしまう可能性もあります。傷跡の修正を希望される場合、下記の方法を用いて改善を図ります。 ●ステロイド注射(ケナコルト)(傷を凹ませる効果が期待できます。) 効果が期待出来るまで、1ヶ月に1回の治療を繰り返す可能性があります。 ●CO2 レーザー照射(術後3ヶ月以降) 傷を削り、目立たなくします。 ●切開法(術後3ヶ月以降、傷の赤みが消えたうえで)再度、切開し縫合いたします。 ※傷を完全に消す事は不可能であり、目立たなくするという目的であることをご了承下さい。また、個人の体質的な要因が大きいため、傷跡修正には限界がありますことをご理解ください。 |
| F) 涙管(るいかん=涙の流れる管)の損傷 | 手術により目頭の涙管が傷つくと、涙の流れが悪くなり目に涙が溜まりやすくなります。 非常に稀なことですが、報告例はあります。 |
涙管の損傷が起きた場合は、涙管の通りをよくする処置を行わせて頂きます。 |
| G) 感染(化膿する) | 赤み・腫れ・痛み・熱感が増したり、長く続いたりする場合は、感染の疑いがあります。 | 感染が起きた場合は、抗生剤の投与を行います。 膿が溜まっている場合は、必要に応じて傷を再度開ける、もしくは、新たに切開し、膿を出す処置を行います。 |
| H) 血が溜まる | 術後に傷の中で出血しますと、血が溜まってまぶたが腫れ上がります。 血が溜まったままにしておきますと、感染やしこりを作る恐れがあります。 |
血が溜まった場合、そのままにしておきますと感染やしこり形成の原因となります。出来るだけ早く処置する必要があります。 その際は、再度傷を開け、溜まった血を排出します。 |
| I) 傷が開く | 稀に糸が外れて、傷が開いてしまうことがあります。 | 傷が開いた場合は、再度、縫合いたします。 |
| J) 白目や角膜の損傷 | 大変稀なことですが、可能性は否定できません。手術中、手術器具が当たる、あるいは糸やまつ毛の先端が当たって眼球の表面に傷がつくことがございます。 | 白目や角膜の損傷や眼球に火傷が生じた例も報告されています。その場合、状態に応じた処置や対応を行います。 |
| K) 眼球の火傷 | 大変稀なことですが、可能性は否定できません。手術中に血を止めるための電気メスやバイポーラによって発生した熱で、眼球の表面に火傷を作る可能性があります。 | 白目や角膜の損傷や眼球に火傷が生じた例も報告されています。その場合、状態に応じた処置や対応を行います。 |